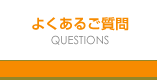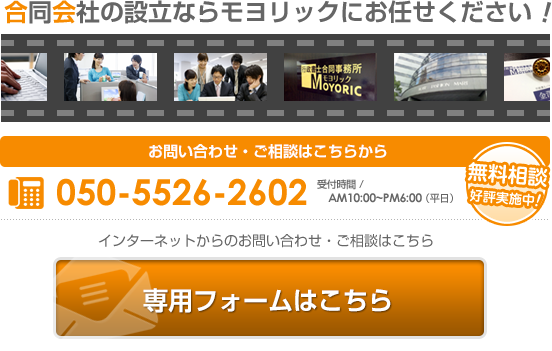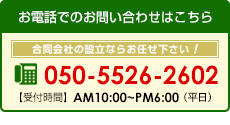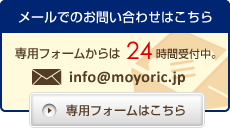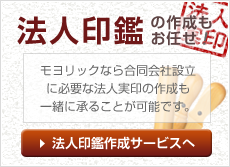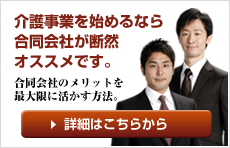合同会社(LLC)における利益の配当
合同会社(LLC)においては、社員は、原則として、いつでも、利益の配当を請求することができます。
そして、利益の配当を請求する方法その他利益の配当に関する事項については定款で自由に定めることができますので、利益の配当に関する事項について定款で定めた場合は、定款の定めにしたがうことになります。
定款で定めることができる事項としては、利益の配当を請求することができる時期・回数、当期に配当する利益金額の決定方法などがあります。
なお、後述の「利益額」を超える利益配当の請求に関しては、定款などで利益配当を請求できる場合であったとしても、合同会社は社員からの利益配当の請求を拒むことができます。
合同会社における利益配当の制限
合同会社は株式会社と同じく有限責任の会社ですから、合同会社の財産が減少する利益の配当を無制限に認めると、合同会社の債権者が不利益を被ることになり不都合です。
そこで、合同会社においては、債権者保護のため、配当可能な限度額が定められており、配当可能な限度額を超える利益の配当はできないことになっています。
この配当可能な限度額は、合同会社全体での限度額(下記A)と社員個別での限度額(下記B)があり、いずれか小さい方の額が、最終的な配当可能限度額となります。 この最終的な配当可能限度額のことを、法律上「利益額」といいます。
利益額(配当可能限度額)の基準
A 合同会社全体での限度額 配当する時点における利益剰余金の額
B 社員個別での限度額 既に分配されている利益の額から既に分配された損失の額および既に配当を受けた額を減じた額
【注意】
A、Bのうち小さい方の額が「利益額」となります。合同会社は「利益額」を超える配当請求を拒否できます。
違法配当を行った社員の連帯責任
上述の利益配当の制限に違反して「利益額」を超える違法な利益配当が行われた場合には、当該違法配当に関する業務を執行した社員は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、当該違法配当を受けた社員と連帯して、配当額に相当する金銭を合同会社に対して支払う義務を負います。
この義務は、原則として免除することができません。
ただし、例外として、利益の配当をした日における利益剰余金の額を限度として当該支払義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、利益剰余金の額を限度として当該支払義務が免除されます。
違法配当を受けた社員に対する請求
利益額を超える違法配当が行われた場合に、その利益配当に関する業務を執行した社員が、配当額に相当する金銭を合同会社に対して弁償したとします。
この場合、原則として、業務執行社員は違法配当を受けた社員に対して配当額に相当する金銭を請求することができます。
しかし、違法配当を受けた社員が、違法配当であること(=配当額が利益額の制限を超えていること)を知らなかった場合は、例外として、業務執行社員からの請求に応じる義務は負わないとされています。
ただし、この例外的な場合であっても、合同会社の債権者は、違法配当を受けた社員に対して、配当額に相当する金銭を支払わせることができます (配当額が、債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合は、債権額までの金銭を支払わせることができます)。
期末に欠損が生じた場合の責任
利益配当が配当制限に違反して行われたものでなかったとしても、合同会社が利益配当をした結果、配当した事業年度の末日に「欠損額」(※1)が生じる場合があります。
この場合、当該利益配当に関する業務を執行した社員は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、合同会社に対して、当該利益を受けた社員と連帯して、その欠損額を支払う義務を負います。
ただし、当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額を支払えば足ります。 なお、この支払義務については、総社員の同意がなければ免除することはできません。
※1【欠損額について】
下記のAの額からBとCの合計額を減じて得た額(ゼロ未満の場合はゼロ)が「欠損額」とされています。
つまり、「欠損額」=A-(B+C)です。
<欠損額の基準>
A ゼロから「当該利益配当をした日の属する事業年度の末日における資本剰余金の額および利益剰余金の額の合計額」を減じて得た額
B 当該利益配当をした日の属する事業年度に係る当期純損失金額
C 当該事業年度において持分の払戻しがあった場合における次の(イ)から(ロ)の額を減じて得た額(ゼロ未満の場合はゼロ)※2
(イ)当該持分の払戻しに係る持分払戻額
(ロ)当該持分の払戻しをした日における資本剰余金の額および利益剰余金の額の合計額
合同会社電子定款作成サービスのご案内
「費用と手間を省いて合同会社を設立したい!」
という方は、合同会社電子定款作成サービスがお勧めです。
- 電子定款の活用で設立費用が安くなる!
- 専門家が作成した電子定款のひな形が使えるから安心!
- 印紙代4万円を節約。コスト削減!
一般の方はもちろん、専門家(税理士、会計士、司法書士、弁護士等)の先生方にも多数ご利用頂いております。
自分で出来る!合同会社設立キット販売中 12,600円
当キットをダウンロードして手続きを進めて頂ければ、最短1日で設立手続きは完了します。
- 少しでも安く設立を済ませたい方
- 時間があるので自分でも動ける方
- 自分自身も手続きに携わりたいという方
- 超特急で今日中にでも登記申請を完了させたい方(法人実印の作成など事前準備は必要です)
自分で出来る!合同会社設立キットでは、設立手続きに必要な書類一式の雛型及び書類作成マニュアルを同梱しております。現物出資にも対応。
会社設立実績1500社を超える専門家(行政書士法人MOYORIC&行政書士法人WEITHNESS)が、一般の方でも簡単に設立手続きが出来るよう作成しました。どうぞご活用下さいませ。
【関連ページ】
- 合同会社ってどんな会社?
- 介護事業には合同会社が最適?
- 介護事業を行う場合の定款の書き方は?
- 不動産投資と合同会社の設立について
- FX法人の銀行口座の審査に通りやすい合同会社の設立は可能か?
- 1人で起業するなら合同会社?
- 合同会社設立、変更の登録免許税は?
- 合同会社の代表者って?
- 合同会社の代表者(代表社員)を2名以上で設立する場合の手続きについて
- 複数の代表社員で合同会社を運営する場合のメリット・デメリットとは?
- 合同会社の業務執行社員とは?
- 業務執行社員は労災や雇用保険には加入できるのか?
- 合同会社の職務執行者とは?
- 合同会社の社員が死亡したらどうなる?
- 合同会社の持分とその相続について
- 合同会社が倒産してしまった場合の社員の責任は?
- 利益の分配方法が自由?
- 設立日に希望がある場合は?
- 未成年でも設立はできる?
- 現物出資って?
- 合同会社の略称・略語は?
- 名刺の記載方法、肩書きは?
- 合同会社に社会保険加入義務はある?未加入の場合のペナルティーは?